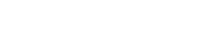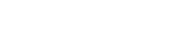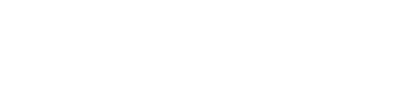バセドウ病は完治する? (ばせどうびょうはかんちする?)
バセドウ病は「完治」のない、付き合っていく病気
結論からお伝えしますと、バセドウ病は「完治」しない病気です。とはいえバセドウ病は治療を適切に行えば、症状はなくなり、運動制限も特になく、健康な時と同じような生活を過ごすことができます。
薬の投与がなくても甲状腺機能が正常化し、症状がなくなることを「寛解」と呼びますが、バセドウ病はこれを目標に治療していくことになります。
症状がなくなっても、再発のおそれがある
バセドウ病に対して、抗甲状腺薬による治療がうまくいけば、薬を飲む必要がなくなる患者さんは一定数います。しかし、そのような場合でもしばらく経過してから、バセドウ病が再発することがあるのです。つまり、甲状腺が残っている限り再発のリスクは残ると言えます。そのため、内服の治療がなくなっても、定期的に再発していないかの経過観察は必要となります。
手術で甲状腺を全部摘出した場合には再発はしませんが、この場合は甲状腺ホルモンを補う甲状腺ホルモン剤を一生涯内服する必要があります。
治療方法について
バセドウ病の治療方法は、大きく分けて以下の3つです。・薬物治療
・放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)
・手術
ほとんどの場合でまずは薬物治療を行います。一般的に1〜2ヶ月ほどもすれば、動悸、体重減少、倦怠感などの甲状腺中毒症状は少なくなり、快適に生活できるようになります。
2年間の薬物治療を経ても投薬を中止できない場合や、副作用によって投薬の継続ができない場合は、別の治療方法に変更することがあります。
放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)は、カプセルを内服するだけの治療ですが、甲状腺を小さくしてはたらきを弱くしてしまうので、半分以上の方は甲状腺ホルモンを補う投薬が必要となるのが注意点です。
また、甲状腺の大きさなどによって手術も行われます。全摘出となるため、術後には必ず甲状腺ホルモン剤の補充を行う必要があります。
具体的な治療内容については、下記の記事などに記載しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。
治療の副作用や合併症
バセドウ病の治療は、治療方法によって副作用や合併症を伴います。まず投薬による治療では、かゆみ・じん麻疹、肝障害、無顆粒球症などを伴う場合があります。無顆粒球症は、白血球が少なくなり感染症になりやすい状態となる重篤な副作用のため、投薬開始後は定期的に血液検査を行い異常がないかを確認します。
アイソトープ治療では、甲状腺ホルモンが減ってしまうため補充が必要となることが挙げられます。また妊娠の前に行うと、TRAbが上昇して新生児バセドウ病のリスクがあるため、1から2年は妊娠の予定がないことを確認してから行います。
手術の場合は、甲状腺を全摘出するため、甲状腺ホルモンを補充するための薬を一生涯、内服する必要があります。また術後は稀に声帯麻痺や手足の痺れが起こる場合がありますが、多くは一時的なもので時間とともに回復します。
日常生活における注意点
バセドウ病の治療では、2から3年で約半数の方が抗甲状腺薬の内服をやめられる状態となり、発症前と変わらない日常を送れるようになります。ただし、甲状腺が残っている限り再発のおそれがあるため、定期的な検診による経過観察を怠らないようにしましょう。また、甲状腺ホルモンのコントロール不良の際、生命を脅かす甲状腺中毒症状態に陥ることがあります。甲状腺クリーゼと呼ばれ、投薬を勝手に中止してしまった際や、感染症が引き金となって起こりうる症状です。
バセドウ病は完治がなく、再発や甲状腺中毒症状態となる可能性のある病気です。定期的な検診と必要な投薬・治療を怠らずに付き合っていきましょう。